皆さんは生物を習ったときにリソソームという細胞内小器官のことを聞いた覚えがありますか?
リソソームではエンドサイトーシスを通じて細胞外から取り込まれた物質や、細胞内の老廃物を分解する細胞内のごみ処理場の役割があります。
このごみ処理場は基本的に酸性状態に保たれており、適度な酸性状態が維持できなくなると老廃物の分解が出来なくなってParkinson病やリソソーム病などの病気に繋がってしまうことが知られています。
今回は6月26日にCellに掲載された、リソソームの酸性環境調整メカニズムを明らかにした下記の論文について紹介したいと思います。
リソソームは、V型ATPアーゼというポンプでプロトン(H⁺)を中に送り込み、酸性環境を作ります。一方で「プロトンをゆっくりと外に出す」仕組みについては解明されていませんでした。本研究ではリソソームに局在するSLC7A11というアミノ酸のトランスポーターが、アミノ酸の輸送を通じて間接的にアミノ酸を運び出しているということが明らかになりました。
タイトルは「SLC7A11 is an unconventional H+ transporter in lysosomes」です。オープンアクセスで全文を読むことができます
酸を「入れる」機構は知られていた。でも「出す」仕組みは?
プロトンをリソソームから外に出すトランスポーターについてはTM175というトランスポーターが報告されていましたが、この輸送体はRapidな輸送を司っており、定常状態でのゆっくりした輸送については分かっていませんでした。
実際にFigure1BでBafilomycinというV型ATPアーゼを阻害する試薬を使うと、Lysotrackerで標識する細胞内の酸性環境が徐々に消失することが分かります。これがTM175のノックアウト細胞でも認められることから、研究チームは遅いプロトンのリークを司るトランスポーターがあるはずと考えました。
そこで研究チームは、これまで知られていなかった「遅いプロトン漏出経路」の正体を探るため、約60種類のリソソーム膜タンパク質に着目し、候補遺伝子をひとつひとつノックアウトするスクリーニングを行いました。
このスクリーニングは顕微鏡ベースで行っていますね。60種類ノックアウトするのは大変だったろうと思います。
SLC7A11がプロトン漏れのカギを握っていた!
その結果、ある意外なタンパク質がこのプロトン漏出に関与していることが分かりました。それが SLC7A11です。
このタンパク質は、これまで主に細胞膜に存在し、「シスチンとグルタミン酸を交換するトランスポーター(system x_c⁻)」として知られていました。特に、がんやフェロトーシス(鉄依存性の細胞死)に関係していることで注目されてきたタンパク質です。
しかし今回の研究で、SLC7A11がリソソームの膜にも存在しており、そこでシスチンとグルタミン酸の出入りを通じて“間接的に”プロトンを運び出していることが分かったのです。
どうやってプロトンが漏れるの?
リソソームの中はシスチンが多く、グルタミン酸は少ない。一方、細胞質ではグルタミン酸が多く、シスチンは少ない。この濃度差を利用して、SLC7A11がシスチンを外に出し、グルタミン酸を中に入れるのですが、これらのアミノ酸はプロトン(H⁺)をくっつけたり離したりできる性質を持っています。
そのため、シスチンとグルタミン酸の交換輸送は、**間接的にプロトンを運ぶ手段(プロトンシャトル)**として機能するのです。
彼らはノックアウト細胞への、SLC7A11の野生型と輸送機能が阻害された変異型の戻し実験でこの輸送機能が重要であることを示しています。
あと面白いのはLysosome単体をin vitroで抗体によって取り出して、PureなVitroの環境でもこのタンパクが重要であることを示していますね。(Figure3の後半)
SLC7A11がないとどうなる?
では実際にこの機能が阻害されるとどうなるのか。
SLC7A11を欠損させた細胞では、リソソーム内の酸性度が“過剰”になり、分解機能が低下してしまいます。すると、分解されるはずの物質が蓄積し、リソソーム病のような表現型(コレステロールやリポフスチンの蓄積、大型化など)を示しました。
また、こうした異常な酸性環境は、フェロトーシスの引き金にもなります。逆に、pHをアルカリに傾ける試薬(クロロキンなど)を投与すると、こうした障害が改善されました。
パーキンソン病との関連も?
さらに、このSLC7A11の機能異常は、神経細胞内でα-シヌクレインの凝集を促進し、パーキンソン病の病態に関わる可能性も示唆されました。
気になった点
とても面白い研究ですが幾つか気になった点がありました。
・いくつかの実験はSLC7A11の阻害薬を使っていますが、これらはリソソームのSLC7A11に届くのか検証されていないと思います。Erastinなどは本来細胞表面のSLC7A11を構造的に阻害する試薬なので、どのようにリソソームのSLC7A11に届いているのか疑問でした。
・NACなどROSのスカベンジャーがリソソームのpHに無効であることは示していますが、Ferroptosisについて行っていないようです。クロロキンでレスキュー出来ていることが証拠になっていますが、SLC7A11欠損によるフェロトーシスがリソソームの異常によるものかはまだ検証が必要かなと思います。
まとめ:リソソームの“抜け道”を調整するSLC7A11
この研究は、これまで謎だった「リソソームからのプロトンの緩やかな漏出」という現象の一端を明らかにしました。
- SLC7A11はリソソーム膜上で機能するアミノ酸トランスポーター
- その働きが、リソソーム内のpHバランスに重要
- pHの乱れが神経変性や細胞死を引き起こす
という新しい発見です。
今後、SLC7A11の活性を制御することで、リソソーム病やパーキンソン病、さらにはフェロトーシス関連の疾患に対する新たな治療戦略が開けるかもしれません。

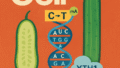
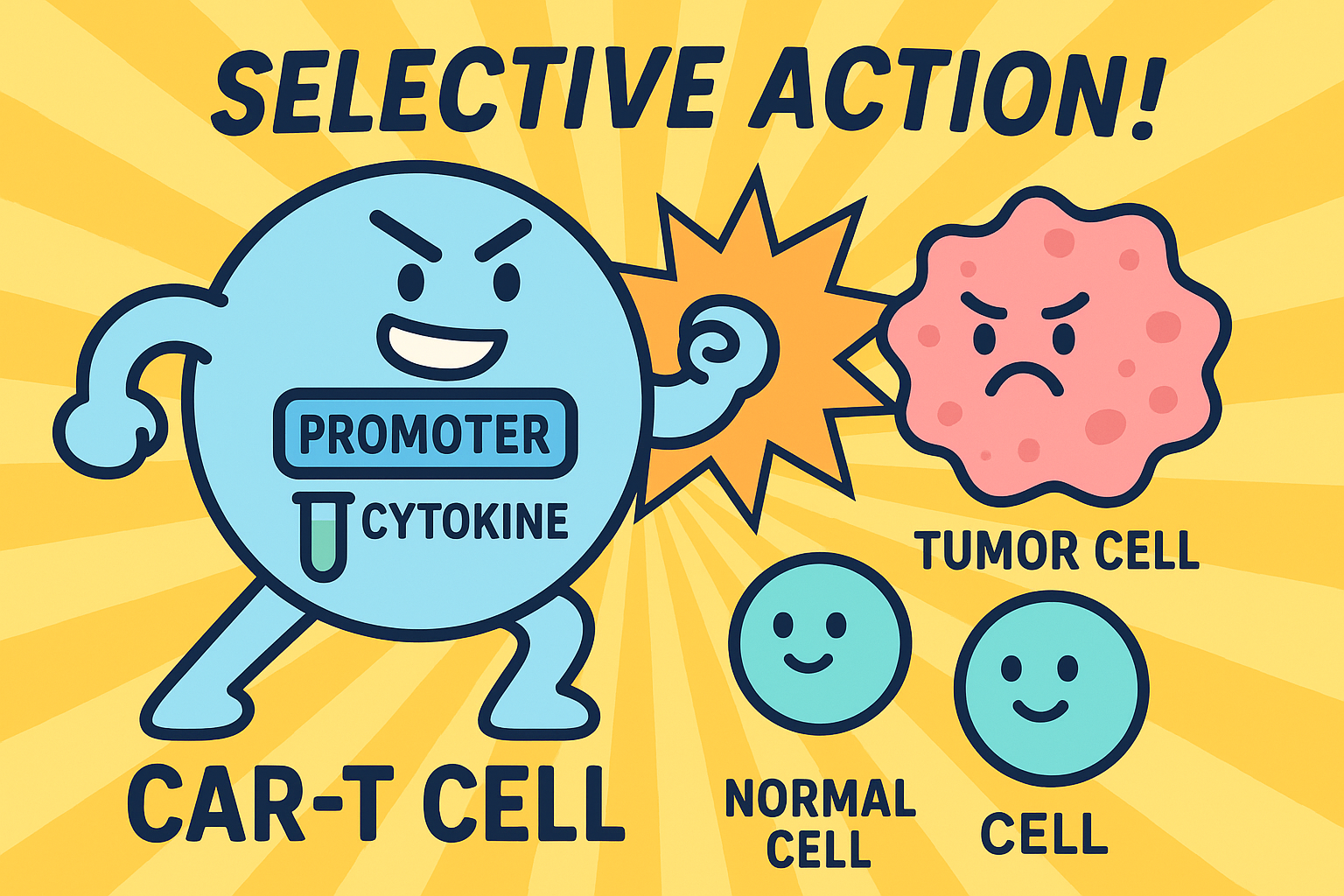
コメント