研究成果は社会に還元されるのが望ましいですが、それと同時に著作権が守られる必要があります。論文中の自然科学上の知見自体には著作権はないようですが、それらを文章として表現したものには著作権があります。(https://www.ruconsortium.jp/asset/196.pdf)
こういった科学論文の紹介についても著作権的にどうなのか自信がなかったこともあり、基本的に論文の画像は使わないようにして、イラストやの画像を使ったりChatGPTに作ってもらったりしていました。
しかし実際に論文紹介をやっていると、文字だけではどうにも説明が難しいところがあり、論文を読みなれていない人に生命科学に触れて欲しいという本来の趣旨から離れてしまうな~と感じていました。
私なりに調べていると条件を満たしていれば、論文の画像を商用利用することも可能なようなので、今後はそういった論文については画像も転載して解説しようと思います。(注意!:これはあくまでこのブログの管理人の方針なので、もしこれに従って雑誌から多額の金銭を求められたとしても、責任を負うことはできませんので気を付けてください。)
まず初めに注意しないといけないのはOpen access=商用利用可能ではないことです。近年は世界的にOpen accessを推進する動きもあり、Nature本誌でも掲載料を多く払ってOpen accessになっているものもあります。これは研究資金提供機関(NIH, EU, UKRI など)が、研究成果はOpen accessで公開すべきと強く求めるようになっており、一部の予算はOpen accessでないと出版できないからです。
しかしOpen accessであっても著作権は出版社やAuthorに帰属しており、商用利用やブログの転載などの可否についてはCreative commons 4.0というルールがあります。(Creative commons Japan: https://creativecommons.jp/licenses/)
これはインターネット時代の新しい著作権のルールで、NatureであればRights and Permissionsのところに記載されています。下記はNature communicationsのある論文の例です。
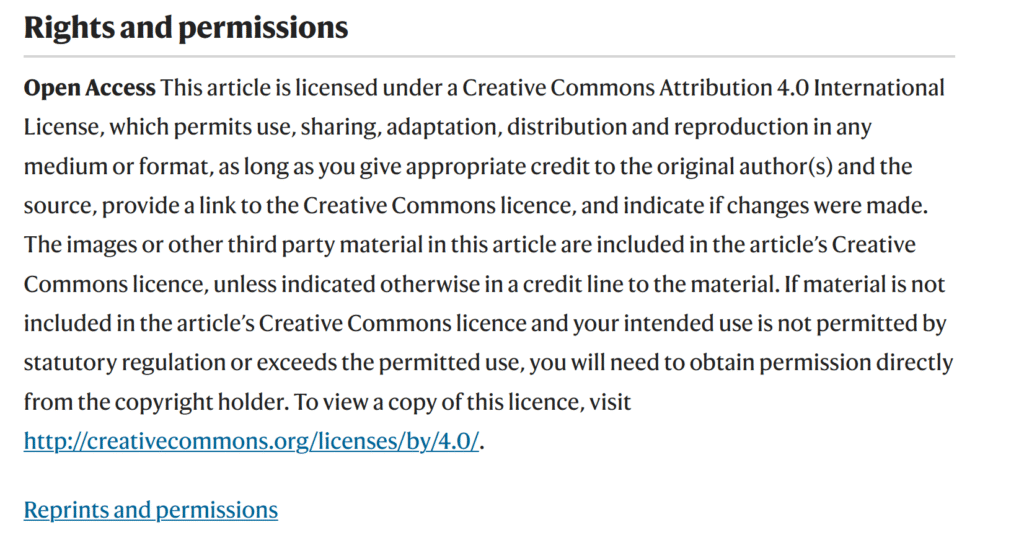
ここでこのリンクをクリックすると下記のページに飛びます。(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
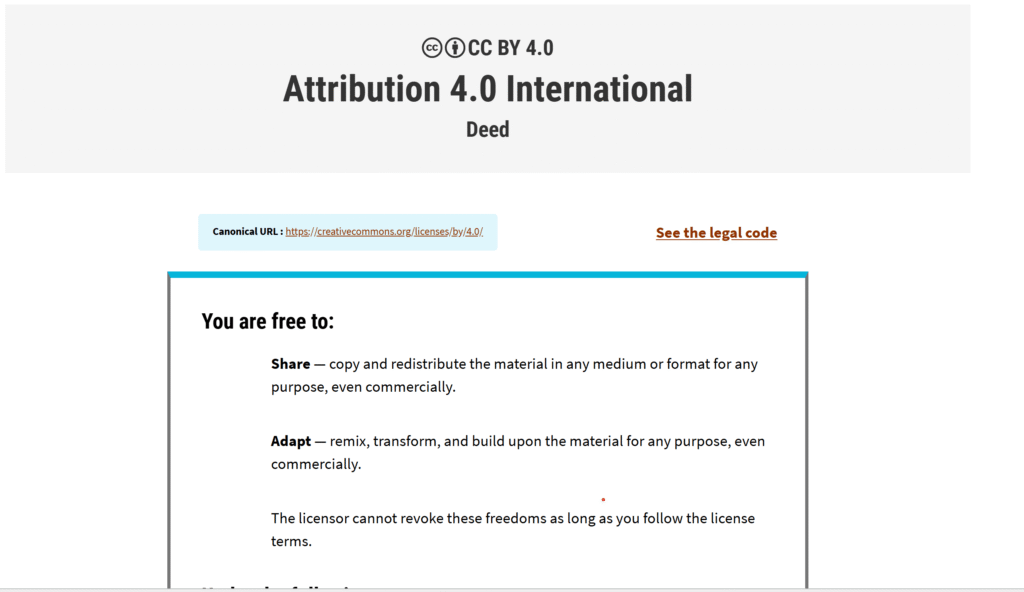
このページにあるこのマークが転載できるかのマークになっています。

Creative commonsには4種類のマークがあり、組み合わせによって6種類のパターンがあります。
((Creative commons Japan: https://creativecommons.jp/licenses/より)

BY(表示): 作品のクレジットを表示すること、基本的にすべてのCCに付与される
ND(改変禁止): 元の作品を改変しないこと
NC(非営利): 営利目的に利用しないこと
SA(継承): 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること
これを踏まえるとNDは日本語で解説しているのを改変ととられた場合に、問題になる可能性があります。また広告がつく可能性がある場合、NCも使用できません。このへんもCreative commons Japanのオープンアクセスについての記事に書いてあります。
なので基本的にこの論文で紹介するものはOpen accessでかつBY単独、もしくはBY-SAの場合は改変したことを明示して同じCCのライセンスを付与して公開することにします。
著作権を守りつつ、できるだけ分かりやすく論文紹介ができるようBrush upしていきたいと思います。
もし著作権的に問題のある記事がありましたら、管理人まで連絡をいただけると幸いです。
このブログの問い合わせ欄でも、XのDMでも大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
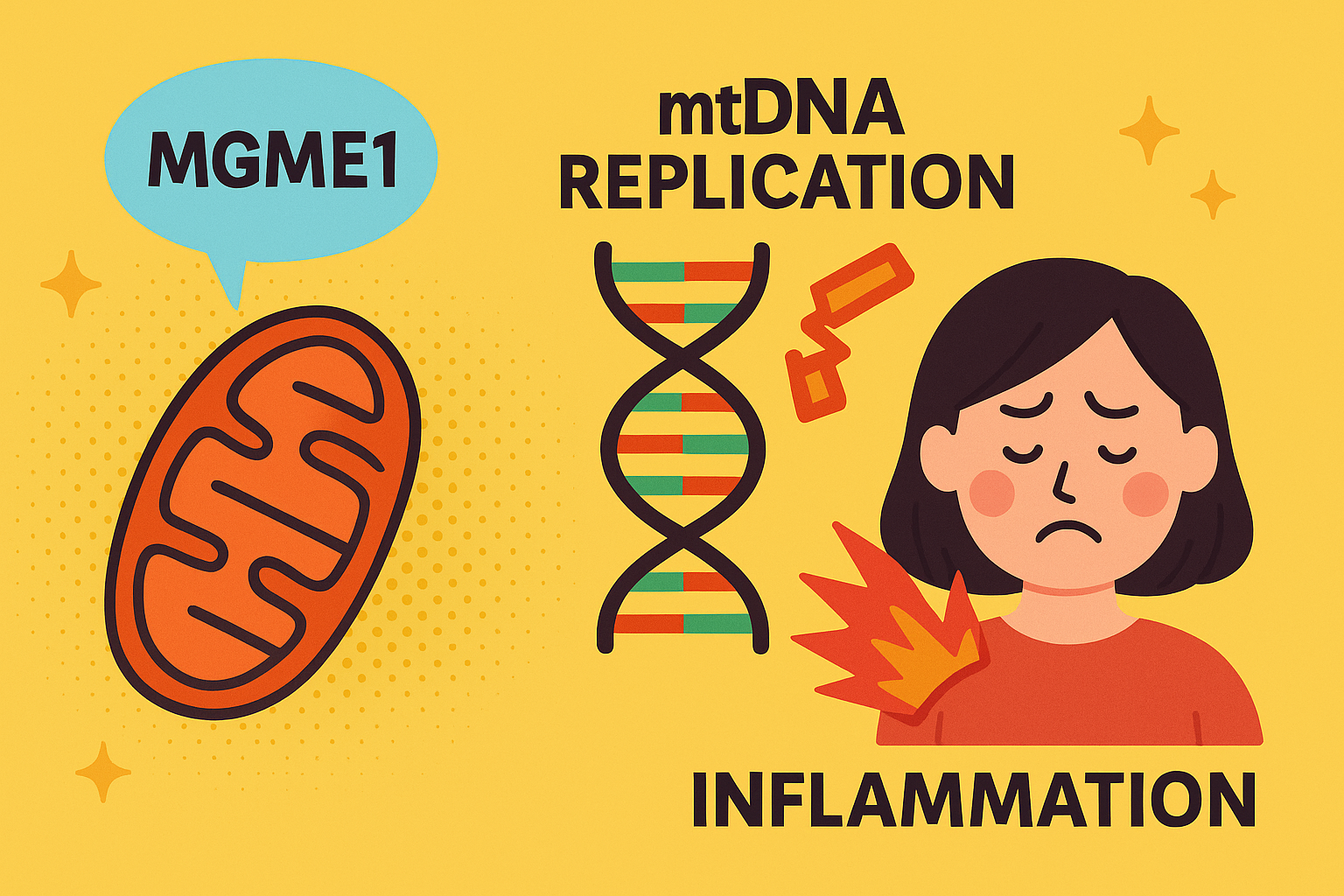
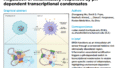
コメント